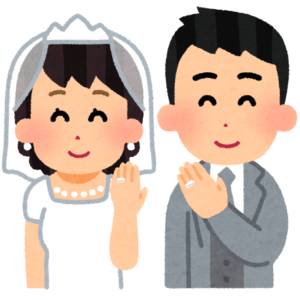離婚するときに決めること
この記事を書いたのは:平田 伸男

離婚をする際、何をすればいいのか、何を決めればいいのか離婚の進め方が分からない方も多いと思います。離婚では下記に記載するものだけを決めるだけではありませんが、一般的には①離婚、②親権、③養育費、④財産分与、⑤慰謝料、⑥年金分割、⑦面会交流を決めることになります。
1 離婚
まず、離婚するか決めなければ、相手との話は進みません。離婚するかどうか迷っている方もいらっしゃいますが、自分で離婚するかどうか決めなければ弁護士もなかなか的確なアドバイスができません。
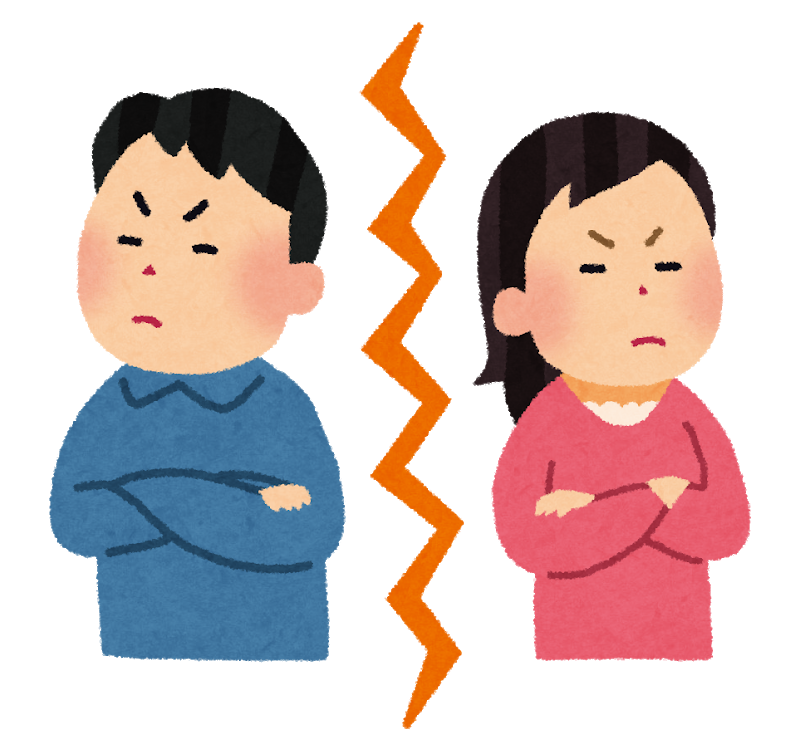
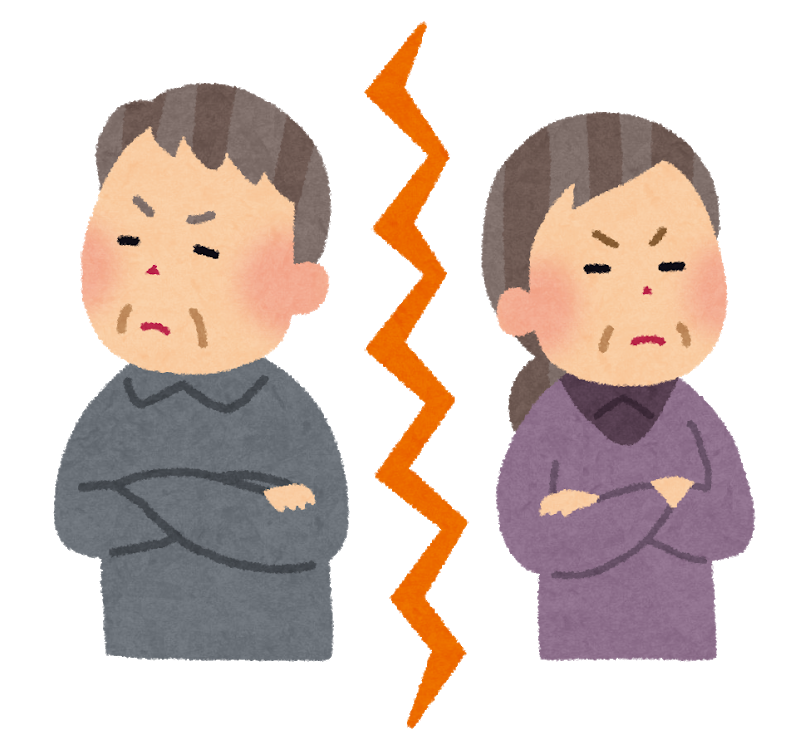
まずは、離婚するかどうかをはっきりさせましょう。
2 親権
夫婦の間に未成年の子がいる場合、離婚に際してどちらが親権者になるか決めなければ離婚することができません。親権は100か0しかないので、争いになる場合、なかなか話合いでまとめることは難しいかもしれません。
3 養育費
親権者が決まった場合、親権者でない方の親は養育費を支払う義務が生ずることとなります。
養育費については、親のそれぞれの年収、子の人数と年齢などによって大まかな金額が決まります。
裁判所が養育費算定表をホームページに載せているのでこれが参考になります。
4 財産分与
結婚後、夫婦生活を送ってきた中で形成してきた財産については財産分与として夫婦で原則半分ずつ分けることになります。

婚姻前から有していた財産や相続した財産などは特有財産といって財産分与の対象になりません。また、借金がある場合などは、プラスの財産とマイナスの財産を差引きして残った財産を分けることになります。
不動産や未公開株式など算定が難しい財産もあるので、しっかりとした査定が重要となります。
5 慰謝料
慰謝料について、離婚を言い出した方が支払わなければならないと勘違いされている方もいますが、どちらが離婚を言い出したかということで慰謝料が発生することはありません。

慰謝料は、離婚の原因となる有責な行為をした場合に生じるもので、具体的には不貞行為やDVなどが挙げられます。このように、有責な行為がなければ慰謝料は生じないので、性格の不一致で離婚する場合には離婚に伴う慰謝料は発生しません。
6 年金分割
年金分割は婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金や共済年金を分割して、それぞれ自分の年金とできる制度です。
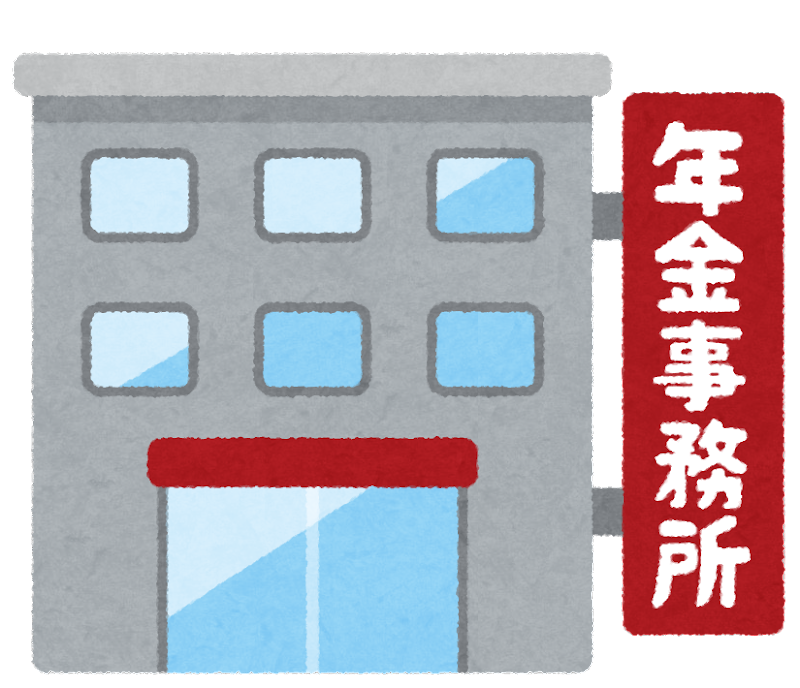
年金分割は原則として2分の1ずつに分けることとなり、3号被保険者の方は相手方の同意を得ずに一方的に年金分割をできる場合があります。
7 面会交流
面会交流は、親権者と違い決めなければ離婚できないものではありません。
近年、非監護親と子の交流が重視されるようになり、離婚時に面会交流の日時や方法を決めることが多いです。実務的には月1回程度の面会交流とする場合が多いです。
8 まとめ

以上のように、離婚するには多くのことを決める必要があります。相手と冷静な話し合いができればいいですが、相手が話に応じてくれことや話合いにならないこともあります。
しかし、弁護士を依頼することにより、離婚にあたって何をどのように決めるのかということや話したくない相手方との交渉を任せることもでき、精神的な安心感も得られます。
離婚でお困りの際は一度、旭合同法律事務所にご相談ください。
こちらもご覧ください関連記事

この記事を書いたのは:
平田 伸男